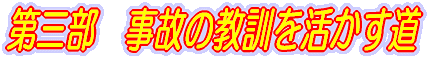2009.5.1.「機関誌 海洋だより」記載文より、ホームページに転載公開。2021.12.リニュアル公開 musick 白鳥の湖

北九州市若松区響灘脇之浦、国道から300mの遭難事故現場で花をそえ祈る妻
自然界の海と向き合う魚釣り、危険を感じませんか?
私達釣り人は自然を相手にした、お魚釣りを楽しんでいますが、そこには危険がいっぱいあります。
自分は大丈夫!!
これぐらい出来る!!
なんとかなる!!
そんな想いで釣りをしていることが、しょっちゅうありますね。
オォー危なかった!!
滑って転んで、海に落ちそうになり、岩場で、テトラポットで、渡船の乗り降りで、危なかったこと、たくさんありますよね。
私も、クラブ員も、仲間達も、みんな魚釣りでケガをしたことがあります。
ケガしたことがない人などありません。ただ、そんなケガで良かった。
これが私達の本当の現実なのです。
磯釣りは当然のようにライフジャケット(救命胴衣)を着けますが、波止や岸壁の釣りでは、9割以上着けている釣り人はいません。
危険な海に直面しながら、朝早くからナイター釣りまで、ごく平凡に私達はお魚釣りを楽しんでいます。個人的な釣りをする方だってたくさんいます。
一人で楽しむ釣りも良いでしょう。仲間達と一緒に楽しむ釣りも良いでしょう。釣りは日頃のストレスを発散させる為にするものですから、自分の好きな方法で楽しむことが最も大切です。
しかし、自由な魚釣りも、もし貴方が命に関わるような事態になったらどうしますか。十分な対応ができるような装備とか、危険察知する能力とか、知識や身体能力などありますか? 特に個人レベルの釣行が多い方なら、なおさら危険が伴います。
事故に遭遇しない釣行を考えたいと想います。相手が超大な自然ですから、何が起きるか分からないのです。
釣り人の自己(事故)責任とはなんだろう。
私達釣り人は自然界に対して自由、気まま、好き勝手に遊んでいますが、ある面、自然界は人間に対して優しくもあり、荒々しい結末を下すこともあります。
そこに海があり、魚がいるから釣り人が竿を出す。ゲームフィッシングは自由で自分勝手、ルールもマナーも本人しだい。その中で自己(事故)責任とは、どのような事を言うのでしょうか。
今、釣界でもっとも問題にしているテーマは「釣り人の自己責任」です。
様々な難しい諸問題をトータルで考えると、好きで楽しい遊びの釣りをしている釣り人は、自分自身で身を守ることをイメージし、行動を考え、誰にも迷惑をかけないこと、その上で命の大切さを分かち合い「釣り人の連帯を促す」ことではないてしょうか。
私からの提案です
◎釣行は、必ず家族や友達に連絡して行く。いつ、何処に、だれと、いつごろ帰る。
◎一人の釣行より仲間、友人を誘って行く。
◎悪天気による無理な釣行はしない。
◎磯はもちろん、波止や岸壁の釣りでもライフジャケットを着けたい。
◎いつも身近に20mほどのロープを持つ。
水汲みバケツや活かしビクのロープを利用する
◎テトラポットからの釣りをできる限り避ける。
◎携帯電話は身近に持ち、防水タイプを選ぶ。
◎釣り場ではまず安全確認と、海に落ちたときをイメージし、救助方法等を描く。
◎九州磯釣連盟、規約の中で「海難防止の心得」及び「海難防止規定」を読む。
釣り具メーカーさんにお願いです
ライフジャケット、救命胴衣をもっと普及させ、
ごく普通の身近な釣りでも着用できる薄手のもの、
衣類に近いベストタイプとか、
サイドバックスタイルとか、
ポケットに入れられるもの等。
とにかく短時間でも良い、
海に落ちて数時間身体が浮くようなものです。
釣り人ならずとも、
海で遊ぶとか、
家庭的な常備品として使えそうなものを、
安価で販売してほしい。
浮き輪の代用、2リットルのペットボトル
海に落ちた釣り人を救助する手段として、まず行うことは、釣り人を浮かせることである。
その為にクーラーボックスはもちろん、周辺の木辺でも、浮くものがあればなんでも投げてやる。
浮き輪の代用として2Lペットボトルは2つあれば身体が浮くので、これを常備したい。
私は関門海峡で釣りをする時、いつも車の中にカラの2Lペットボトルを入れている。又、ペットボトルのキャップ、首の部分に紐をくくりつけ、竿立ての三脚のオモリ代わりにも使う。
イザというときに、この紐にロープを繋げ投げてやることを考えている。
磯釣りでも2Lのペットボトルに水か、お茶を入れ、クーラーやバッグにいつも常備している。
最後に
人間は凡人である。
そのとき、その場合はしっかり反省し、頭の中で整理し行動するが、一週間、一ヶ月すると、あの時のこと、教訓をもう忘れている。
わが身でなければよけいに、である。
しかし事故はいつおこるか分からない。
自分の身は自分で守るが、他人の手助けも必要である。
若くもない釣り人は、よりいっそう安全な釣りを心がけたい。
機関誌 「海洋だより」は、会員さんはもとよりOB会員さん、釣り仲間、釣り団体組織、行政から、釣り具メーカーさんまで郵送しています。
身近なお店や交友関係にも手配りをして毎度300部ほど配布しています。
その中で今度の遭難事故、特集記事は、たくさんの方から、ねぎらいの言葉をいただきました。
事故に直面しない行動をとる、そのことを皆で考えたいですね。
| ㈱マルキュー(九州MFG)で、身近にお付き合い頂いている、高園 満さんから、大変貴重なお手紙を頂きましたので紹介させて頂きます。 |
上瀧勇哲 様
前略
二月の「機関誌 海洋だより」の中に、藤崎慶冶さんの遭難記事があり、近場でも、身近な釣り場でも、気を抜いて釣りをしてはいけない事がよく分かりました。
私も、先年、若松磯釣倶楽部の福浦朱竿御大を釣り場で亡くし、御大のよく言われていた
「救命着は何時も身に付けておく。これは自分も助からなくてはいけないが、他人に迷惑を掛けないためでもある」
という教えに、波止でも身に付けて釣っています。
釣り人は、慣れれば、慣れる程、沖磯や荒磯に釣行する程、こんな近場で救命着なんて恥かしい、とか、こんな波止で救命着なんて、ぎょうぎょうしい、など、考えていくものです。
今、関門海峡の岸壁の釣りでも、落水したら、自分で上がれるハシゴも階段も全く有りません。
また、ファミリーの釣りでも、お父さんが自分の子供が転落しても、直ぐ救けきる技術や手段を身に付けてはいないと思います。
私の水汲みバケツは、滑るナイロンロープを外し、丈夫なクレモナロープに替え、30㎝ごとに結び目を作り、長さも7m以上に仕直しています。
落ちた子供に片足を入れさせ、ロープをつかませ、7mあれば北九州の高い波止や岸壁からでも、つなぎ止めたり、引き上げることも出来るようにしてあります。
現在は悪いことに、30mの救命ロープや、ハーケンを打つハンマーなど、釣行に持って行く上物師は少なく、グループによっては全く持ったことも無い。というグループもよく見かけます。
私も「ちぬの詩」の原稿中に、安全のことを書くことも有りますが、格好だけの釣り師が増えているのは確かだと思います。
原稿を書いている間は、少しでも海防など、文中に入れていこうと思っております。
草々
高園 満
追記
今、メーカー2社には、砂浜の渚釣りや、波止釣りでも着用できる救命着を言ってありますが、作るかどうかは分かりません。釣り人の心構えをどうさせるかが問題だと思っています。